八俣遠呂智の段 のバックアップ(No.6)
八俣遠呂智の段 / やまた をろち の段
| 国つ神 / くにつかみ | |
| 老夫(おきな)と老女(おみな)二人(ふたり)在(あり)て 童女(をとめ)を中に置(す)ゑて泣くなり スサノヲの命 汝等(いましたち)は誰(た)れぞ と問ひ賜へば 僕(あ)は国つ神 オホヤマツミの神の子なり 僕(あ)が名はアシナヅチ 妻(め)が名はテナヅチ 女(むすめ)が名はクシナダヒメ | |
| 国つ神 | 高天原に坐す天つ神に対(むかへ)て 此(この)国なる神を云ふなり |
| オホヤマツミ | 記番40 イザナギイザナミの子 |
老夫 老女 童女 / 高天原は大人の姿で生まれ歳をとらないのかも
 |
| アシナヅチ |
[古事記:136] アシナヅチ-ノカミ
・老夫(おきな)アシナヅチ 子はクシナダヒメ
[日本書紀]
・8-本文 アシナヅチ
・8-2 アシナヅテナヅ
・8-3 アシナヅチ
[竹 ヒゴ]
 |
| テナヅチ |
[古事記:137] テナヅチ-ノカミ
・老女(おみな)テナヅチ 子はクシナダヒメ
[日本書紀]
・8-本文 テナヅチ
・8-2 アシナヅテナヅ
・8-3 テナヅチ
[蔓 カゴ]
| ハヤスサノヲ 問ひたまふ 汝(いまし)の哭(な)く由(ゆゑ)は何(なに)ぞ 我(わ)が女(むすめ)は もとよりヤヲトメ在りき 是(こゝ)に 高志(こし)の ヤマタノヲロチ 毎年(としごと)に來て喫(くら)へり 今其(そ)が来(く)べき時 故(かれ)泣く |
 |
| クシナダヒメ ☆ |
[古事記:138] クシナダヒメ
・アシナヅチテナヅチの子 クシナダヒメ
・スサノヲの嫁 一人目 六代(むよ)の子孫(みま)が大国主
これよりヒメに神や命が付かなくなる
[日本書紀]
・8-本文 クシイナダヒメ
・8-1 イナダヒメ
・8-2 マカミフルクシイナダヒメ
・8-3 クシイナダヒメ
[まんが]
・歳は八歳(やとせ)とする
・スサノヲに救はれて嫁になる
・ちびっこにしてお嫁さん
[スミレ ブリ]
 |
| ヤヲトメ |
[古事記:139]
・アシナヅチテナヅチ 我が女(むすめ)は もとよりヤヲトメ在りき
[日本書紀]
・8-本文 ヤタリノヲトメ
[モックリ] (セミの子の名)
| 八俣遠呂智 ヤマタノヲロチ |
| その目は赤かがちの如くして 身ひとつに八頭(やかしら)八尾(やを)有り 亦(また)其の身に蘿(こけ)また檜榲(ひすぎ)生(お)ひ 其の長さは 谿八谷(たにやたに)峽八尾(をやを)に度(わた)りて 其の腹(はら)を見れば 悉(ことごと)に常(いつ)も血に爛(ただ)れてあり |
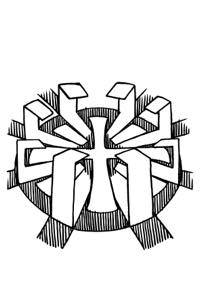 |
| ヤマタノヲロチ ☆ |
[古事記:140] ヤマタノヲロチ
[日本書紀]
・8-本文 ヤマタノヲロチ
・8-2 ヤマタノヲロチ
・8-3 ヲロチ
・8-4 ヲロチ
[古事記伝] ヤマタヲロチ
[まんが]
・大風や大水から守り豊かな実りをもたらし 年(とし)にひとつ摘まむ神
・3番カミムスヒの子としておく
・八人(やたり)のヤヲトメを喫(くら)ふと 八十八(やそまりやそ)俣の大蛇神(をろみかみ)に成れるやも
[フキ]
| アシナヅチテナヅチの容貌(かほかたち) |
| 十五で嫁いで十六で子を生むとする 年ごとにヤヲトメを生む ヲロチが八歳(やとせ)で喫(くら)ふ 年ごとに喫はれて七年(ななとせ)目 |
| 十六歳に八歳に七年 アシナヅチテナヅチは 凡(おほよ)そ三十一(みそじまりひと)歳(とせ) 21世紀半ばまでの栄養と美容では 今の世より20歳年老いて見えるため 50歳くらゐの容貌 |
| 喫(くら)はれたヤヲトメ 死にきとは書かれて居ゐないため まんがでは還って来る |
| 川上の村 |
| 古代の製鉄は 山を崩し岩を砕いて水で砂鉄をより分ける ヲロチは土砂混じりの川の象徴と云ふ 多くの強い酒を作れるほどの コメの蓄(たくは)へのある かなり豊かな製鉄の村 |